三ノ宮から徒歩2分のパソコン修理店「パソコン修理サービス」です!
「パソコンの電源が入らない!」「もしかしてACアダプターが壊れたのでは?」
そんなときに頭をよぎるのが、「USB-Cから充電できないかな?」という発想です。
最近のノートパソコンにはUSB-C端子が搭載されており、スマートフォンのようにケーブル1本で充電できそうなイメージがありますよね。
しかし――結論から言うと、「USB-C充電ができるかどうか」は機種次第であり、単純にケーブルを挿しても通電しないケースがほとんどです。
この記事では、USB-C充電の仕組みや電源故障時の応急対応の現実、そして安全に修理へ進むためのポイントを分かりやすく解説します。
Windows10のサポートが終了しました
Windows10は、2025/10/14にサポートが終了しました。
このまま放置した場合、ウイルス感染する確率が高くなり、ソフトウェアが使用できなくなる可能性がございます。
詳しくは、LINE・メール・お電話でお気軽にご相談ください。
USB-Cポート=充電できる、ではない!

まず理解しておきたいのは、USB-C端子がある=充電できるわけではないという点です。
USB-Cはあくまで「形状(コネクタの形)」の規格であり、「電源供給できるか」は内部の設計次第なのです。
USB-C端子には大きく分けて次の3種類があります:
- データ転送専用ポート(USB 3.xなど)
→ 通常のUSBと同じで、マウス・キーボード・外付けHDDなどの接続用。充電には非対応。 - USB Power Delivery(USB PD)対応ポート
→ 最大100Wまでの電力供給が可能。これが「USB-Cで充電できるノートパソコン」の条件。 - 映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポート
→ 外部ディスプレイに映像を出すためのタイプ。給電は不可のことも多い。
つまり、あなたのノートパソコンにUSB-Cポートがあっても、「PD対応」でなければ電力は入ってこないのです。
USB Power Deliveryとは?
USB Power Delivery(通称:USB PD)は、近年登場した給電規格で、最大20V・5A(=100W)までの電力を安全に送れるよう設計されています。
たとえばスマートフォンでは18〜30W前後ですが、ノートパソコンは消費電力が大きいため、60W以上の電力供給が必要です。
USB PD対応のパソコンなら、ACアダプターの代わりにPD対応の充電器を接続することで起動や充電が可能になります。
しかし、古い機種や安価なノートパソコンではPD非対応であることが多く、見た目が同じでも内部的には電力が通らないのです。
電源が壊れた時の「USB-C充電」の落とし穴

電源トラブル時、「ケーブルを変えたら動くかも?」と考えるのは自然なことです。
しかし、実際には以下のような落とし穴があります。
- PD非対応ポートに差しても充電されない
→ LEDも点かず、電源は全く供給されません。内部回路が給電経路を持たないためです。 - PD対応でも、出力不足だと充電できない
→ 45W対応の充電器を、65W必要なノートに使うと、起動中に電圧が足りず電源が落ちるケースも。 - ケーブルも規格を満たしていないと給電できない
→ 安価なUSB-Cケーブルでは「通信のみ」で、電力が通らないことがあります。 - 根本的な電源基板故障なら無意味
→ ACアダプターでもUSBでも給電されない=内部の電源ICが故障しているケースです。
結論として、「USB-Cで充電できるか」は設計・規格・内部状態の3つが揃って初めて可能になる、ということです。
電源が壊れたときに試すべきチェック項目

パソコンが全く動かなくなったとき、焦ってUSBを試す前に以下の点を確認しましょう。
- ACアダプターが本当に壊れているか?
→ 別のアダプターで動くなら、単なるアダプター故障です。互換アダプターも販売されています。 - バッテリー残量がゼロになっていないか?
→ 長期間使っていないと過放電で電力が完全に枯渇することがあります。 - 電源ランプ・充電ランプの反応は?
→ 点滅している場合は、内部ショートやマザーボード保護回路が作動している可能性も。 - USB-C PD対応かどうかを調べる
→ 型番をインターネットで検索し、「Power Delivery対応」と書かれていなければNGです。
安易に「スマホ用USB充電器」を使うのは危険!
よくある誤解が、「スマホ用USB充電器で代用できる」というもの。
実際にはスマホ用は5V固定(最大15W程度)で、ノートPCに必要な電力(45〜100W)には到底足りません。
結果として、給電不足によりパソコンが点いたり消えたりを繰り返す、あるいは電源回路がダメージを受けることもあります。
また、安価な充電ケーブルの中にはPD通信チップが搭載されていないものも多く、過電流や発熱による故障リスクがあるため要注意です。
USB-C充電対応ノートなら解決できるかも?
もしあなたのPCが「PD対応」モデルなら、純正のACアダプターが壊れてもUSB-C経由で動作できる可能性があります。
例えば、最近の Dell XPS / Lenovo ThinkPad / HP EliteBook / Microsoft Surface / MacBookシリーズ などは、PD充電に正式対応しています。
ただし、それでも以下の条件を満たす必要があります。
- 65W以上のPD対応充電器を使用すること
- 「E-marker」対応ケーブル(高出力対応ケーブル)を使うこと
- バッテリーが完全放電していないこと
それらを満たしても動作が不安定なら、内部の電源制御チップが故障している可能性が高いです。
修理に出すなら「神戸三宮店」へ
もし「電源が入らない」「USB-Cでも通電しない」「ACアダプターを替えても反応しない」という状態になった場合、自己判断での分解は危険です。
電源部分は感電・ショートのリスクがあり、さらに誤ってマザーボードを破損させると修理費用が倍増することもあります。
こうしたトラブルは、パソコン修理サービス 神戸三宮店 での診断をおすすめします。
当店では以下のような対応が可能です。
- ACアダプター・電源基板の動作テスト
- USB-C給電可否の確認
- バッテリー・マザーボードの電流測定
- 必要に応じた部品交換・データ保護
特に「引っ越し後や移動後に動かなくなった」「ホコリで通電不良が起きた」などの相談も多く、部品交換で改善するケースもあります。
まとめ
USB-Cから充電できるノートパソコンは確かに増えましたが、「どの機種でもできるわけではない」という現実があります。
特に電源が壊れている状態では、USB-Cを挿しても意味がないケースが多く、誤った判断はさらなる故障につながります。
最も安全なのは、専門店での診断です。
「電源が壊れたかも」「USB-Cで通電しない」などの不安がある場合は、パソコン修理サービス 神戸三宮店 にぜひご相談ください。
原因を正確に見極め、最短で安全に復旧へと導きます。
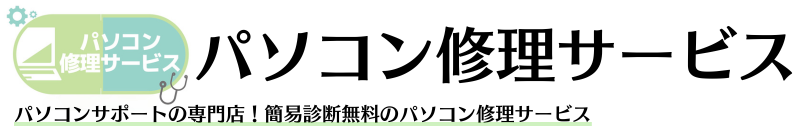
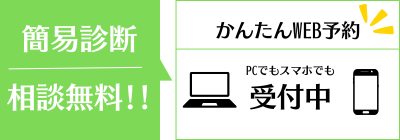
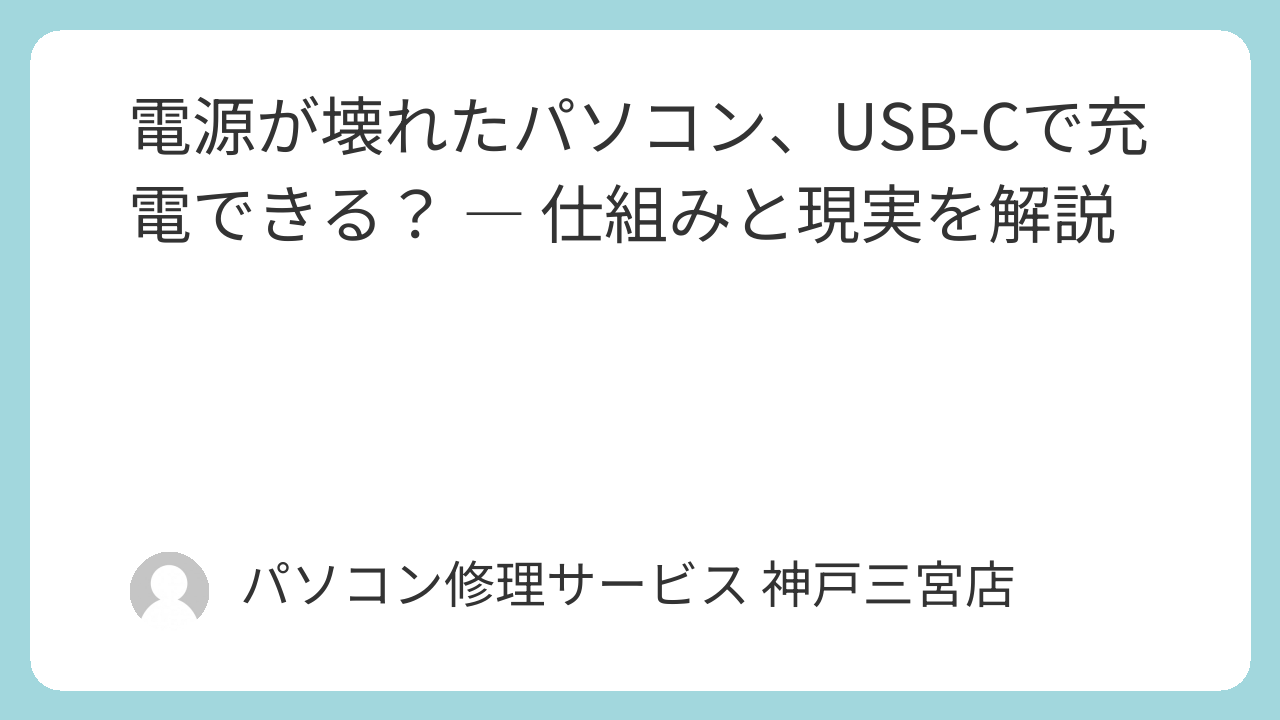

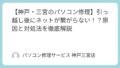
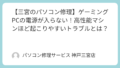
コメント